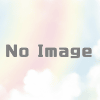お彼岸の意味・由来と期間がいつからいつまでか紹介
本サイトにはプロモーションが含まれています。

お彼岸の季節が近づいてきました。
お墓参りに行ったり、ぼたもちやおはぎを食べたりしていると思います。
しかし、毎年の行事だからという理由で、「とりあえずこなす」という風になっていませんか?
意味を知らなくてもご先祖様を供養するという目的を達成できているとは思いますが、行事の意味を知ることは大事なことではないでしょうか。
そこで、お彼岸の意味・由来と期間がいつからいつまでかを紹介します。
お彼岸の意味・由来
お彼岸は仏教用語
お彼岸という言葉は仏教の用語です。インドの古典言語であるサンスクリット語のParamita(パーラミター)が原点と言われています。
Paramita(パーラミター)は「超える」「渡る」を意味しており、「到彼岸」と訳されます。到彼岸とは、三途の川を挟んで、人間の世界「此岸(しがん)」から仏様の世界「彼岸(ひがん)」へ渡ることです。
人間の世界(此岸)は、欲望や執着など煩悩と迷いの世界ですが、仏様の世界(彼岸)にはそのようなものがありません。しかし、生きているうちは煩悩や迷いが消えることはなく、仏様の世界(彼岸)に渡ることができるのは死後とされています。
それがいつしか、死後の「極楽浄土」と捉えられるようになり、ご先祖の住む世界を「彼岸」と呼ぶようになったのです。
生きている間に仏様の世界(彼岸)へ渡るためには修行が必要と言われていますが、どのような修行なのでしょうか?
お彼岸は修行期間
お彼岸の期間は、六波羅蜜(ろくはらみつ)に由来しています。
六波羅蜜とは、人間の世界(此岸)から仏様の世界(彼岸)へ渡るために行われる6つの修行のことです。
| 布施 | 完全な恵みを施す。 |
| 持戒 | 自らを戒める。 |
| 忍辱 | いかなる辱めを受けても耐え忍ぶ。 |
| 精進 | 日々努力する。 |
| 禅定 | 客観的に自分自身を見つめる。 |
| 智慧 | 真理を見極める。 |
6つの修行を1日ずつ行い、7日目に修行を終えるとされています。仏様の世界(彼岸)へ渡るための6つの修行を行うために、お彼岸は7日間あるということですね。
では、お彼岸が春と秋の2回あるのはなぜでしょうか?
お彼岸が2回ある理由
仏教では極端な考え方を避けており、修行にふさわしい時期を次のように定めています。
- 昼と夜の長さが同じ期間
- 暑さと寒さの中間点
このような時期は1年で2回あります。春分の日と秋分の日です。春分の日と秋分の日は中日と呼ばれています。
春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈みます。そのため、昼と夜の長さがほぼ同じになり、人間の世界(此岸)と仏様の世界(彼岸)が最も通じやすくなると考えられています。
また、春分の日と秋分の日は、季節の変わり目でもあります。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉はここから来ています。昼と夜の長さが同じ期間であり、暑さと寒さの中間点である春分の日と秋分の日が、修行に最適な期間というわけです。
つまり、春分の日と秋分の日の前後3日間、計7日間がお彼岸の期間ということになります。
さて、お彼岸になるとお墓参りをしますが、それはなぜでしょうか?
お墓参りをする理由
「彼岸」は仏教の教えですが、お彼岸にお墓参りするのは、他の仏教国には見られない日本だけの行事です。正式には、彼岸会(ひがんえ)と呼ばれています。インドや中国に、お墓参りの習慣はありません。
お墓参りが行われるようになった時期については諸説あります。
- 聖徳太子の頃から始まったという説
- 平安時代から始まり、江戸時代に年中行事になったという説
古来より日本では、ご先祖様や自然の恵みに感謝する風習がありますが、それらと仏教の教えが結びついてお墓参りするようになったと考えられています。
さて、お墓参りのお供え物に「ぼたもち」と「おはぎ」がありますが、これらはどういった意味があるのでしょうか?
ぼたもちとおはぎの意味・由来


「ぼたもち」と「おはぎ」はほぼ同じ食べ物です。ですが、次のような違いがあります。
| ぼたもち | おはぎ | |
|---|---|---|
| 時期 | 春 | 秋 |
| 由来 | 牡丹 | 萩 |
| 大きさ | 大きめ | 小さめ |
| あんこ | こしあん | つぶあん |
ぼたもちとおはぎの由来
ぼたもちは春の咲く花「牡丹(ぼたん)」、おはぎは秋に咲く花「萩(はぎ)」にそれぞれ由来しています。
江戸時代に「和漢三才図会(わかんさんずいえ)」という百科事典のようなものがあり、その中にこのような記載があります。
牡丹餅および萩の花は形、色をもってこれを名づく
ここから、牡丹餅をぼたもち、萩を丁寧に言っておはぎと呼ぶようになったと言われています。牡丹は大きな花のため牡丹餅(ぼたもち)は大きめに、萩は小さな花のためお萩(はぎ)は小さめに作られます。
あんこの違い
あんこの違いは小豆の収穫時期に関係があります。あんこの原料は小豆ですが、小豆の収穫時期は9〜11月です。
秋のお彼岸は9月で、小豆の収穫時期と重なります。採れたての小豆は皮が柔らかいため、つぶあんとして食べられます。
一方、春のお彼岸は3月です。小豆の収穫時期からは3ヶ月以上が経過しており、皮が固くなっています。そのため、皮を取ってこしあんとして食べられます。
ぼたもちとおはぎの意味
お彼岸に「ぼたもち」や「おはぎ」を食べるようになったのは、江戸時代からと言われています。
あんこに使われる小豆は、悪いものを追い払う効果があると信じられていました。小豆を食べることで邪気を払い、それがご先祖様の供養となると考えられていたのです。
お彼岸の期間
お彼岸の期間は毎年変わります。2020年までのお彼岸期間を見てみましょう。
2015年
春:3/18(水)〜24(火)
秋:9/20(日)~26(土)
2016年
春:3/17(木)~23(水)
秋:9/19(月)~25(日)
2017年
春:3/17(金)〜23(木)
秋:9/20(水)~26(火)
2018年
春:3/18(日)〜24(土)
秋:9/20(木)~26(水)
2019年
春:3/18(月)〜24(日)
秋:9/20(金)~26(木)
2020年
春:3/17(火)~23(月)
秋:9/19(土)~25(金)
※春分の日と秋分の日は、国立天文台の予測に基づいて記載しています。
春分の日と秋分の日は年によって変わります。お彼岸の期間は毎年確認するようにしましょう。
まとめ
国民の祝日に関する法律によれば、春分の日と秋分の日は次のように定義されています。
自然をたたえ、生物をいつくしむ。
秋分の日
祖先を敬い、なくなった人々をしのぶ。
お彼岸の由来を知れば、祝日の意味も少しは分かるかもしれません。
お墓参りをしたり、仏壇に手を合わせたり、普段よりちょっとだけ、ご先祖様に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。