ハロウィンの由来や起源とトリックオアトリートの意味
本サイトにはプロモーションが含まれています。

秋のイベントの一つとして日本でも盛り上がりを見せるハロウィンですが、由来や起源を知っていますか?
ハロウィンとは何なのか、周りに聞かれたときにうまく答えられない人は多いようです。
そこで、ハロウィンの由来や起源とトリックオアトリートの意味についてまとめてみました。
知れば知るほど、ハロウィンが楽しみになりますよ。
ハロウィンの起源・由来はサウィン祭
ハロウィンの起源はサウィン祭と言われています。
ハロウィンの歴史は、およそ2000年前に遡ります。その鍵を握るのは、古代中央アジアからヨーロッパに渡来した民族・ケルト人です。
ケルト人の風習の一つに、サウィン祭と呼ばれる祭りがありました。サウィン祭とは、秋の収穫のお祝いと悪霊払いの宗教的行事です。
サウィン祭の日にちや内容は、ケルト人の暦や考え方と深い関わりがあります。
ケルト人の暦と考え方
ケルト人の暦では、新年は11月1日です。その日は冬の始まりを示し、大晦日にあたる10月31日は、夏の終わりを示しています。31日の夜は、ちょうど夏と冬の季節の境目とされてきました。
ケルト人の信仰では、この時期に「この世」と「霊界」の境目にある門が開き、人間と死者の霊が自由に行き来できると信じられてきました。冬の訪れは、死者の霊が家族を訪ねてくると同時に、「悪いシー」と呼ばれるケルト神話の妖精や悪霊、魔女も出てくる時期でもあるのです。
その悪霊から身を守るために、毎年10月31日に悪霊払いの儀式・サウィン祭を執り行ったとされています。
この夜は、魔除けのかがり火が焚かれ、作物と動物の犠牲が炎にくべらます。村人たちは、かがり火が燃え上がると他のすべての火を消します。次に、祭司たちが火のまわりで踊りを始め、それを合図に夏は冬へ移るとされていました。
そして11月1日の朝、村人たちは、祭司に与えられたかがり火の燃えさしを持ち帰り、かまどの火を新しくつけ儀式は終わります。かがり火の魔除けの力によって、「悪いシー」たちが家の中に入るのを防いだと言われています。
ハロウィンの起源は諸説あります。
この他にも、カトリック系移民がケルト系移民を侵略した歴史があり、2つの民族の関わりによって現在のハロウィンの形ができ上がったという説もあります。
だとすれば、ハロウィンは、キリスト教に関係する祭りなのでしょうか?
ハロウィンとキリスト教の関係
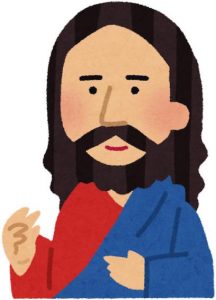
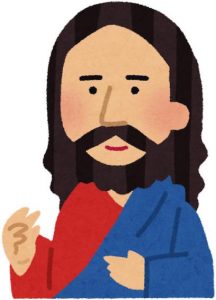
キリスト教の宗派の一つ・カトリック教会の諸聖人の日は、11月1日です。
諸聖人の日とは、すべての聖人と殉教者(信仰のために命を失った人)を記念する日です。この日は祭日であり、信者は儀式に参加して、花を持ってお墓参りをします。
諸聖人の日の前夜である10月31日がハロウィンとなると、この2つのイベントは一見すると繋がりがあるように見えます。
しかし、ハロウィンはキリスト教と関係ないとされています。
日付がほぼ一致していることに関しては、2つの見解があるとされています。
- カトリック教会が異教の祭りを取り込んだ。
- カトリック教会が異教の祭りをつぶすためにその日に設定した。
いずれにせよ、現在のハロウィンは、特にアメリカの民間行事として定着しており、本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっているようです。
ハロウィンでかぼちゃが飾られる理由


ハロウィンでは、ジャック・オー・ランタンと呼ばれる、かぼちゃをくり抜いて中に明かりを入れたランタンが飾られます。これは、ハロウィンのシンボル的な飾りつけです。
なぜ、ハロウィンのシンボルがジャック・オー・ランタンで、かぼちゃなのでしょうか?
ジャック・オー・ランタンとは、アイルランドやスコットランド版の「成仏できない火の玉の霊」のことです。その霊の人物の名前がジャックなのです。
ジャックは「ランタンを持ってこの世を彷徨っている死者」として登場する、アイルランドやスコットランドに伝わる神話上の人物です。
伝説上の彼は、萎びて転がっていたカブをくり抜いて自らランタンを作り、それを持って夜の闇の中を彷徨い歩いています。
しかし、ハロウィンがアメリカに渡ったとき、その時期に手に入りやすかったかぼちゃを用いてランタンを作ったことから、かぼちゃのランタンが世界中に広まったと考えられています。スコットランドでは、現在でもカブが使われているそうです。
ハロウィンとは一見なんの関係もないジャック・オー・ランタン。
しかし、ハロウィンの夜に「死者の霊がこの世を訪れる」のであれば、街を彷徨う死者の霊であるジャック・オー・ランタンが出てきても不思議ではないですね。
ジャックの伝説はなかなか面白い物語ですので、読んでみてはいかがでしょうか。
トリックオアトリートの意味


Trick or Treat(トリック・オア・トリート)
日本語では、「お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ」と訳されています。ハロウィンでは、子供たちはお化けに変装し、家々を訪ねて「トリックオアトリート!」と言ってお菓子をもらいます。
それはなぜでしょうか?
子供たちがお菓子をおねだりする行為の由来
子供たちがお菓子をおねだりする行為の由来には、カトリック教会が関係しているという説があります。
カトリック教会の諸聖人の日(すべての聖人と殉教者を記念する日)は11月1日です。その翌日11月2日に、「死者の日」というものがあります。この日には、祈りの儀式が行われます。
祈りの儀式では、死者を弔い捧げられるソウルケーキというものが使われます。ソウルケーキとは、小粒のレーズンと・シナモン・ナツメグが入った平たい卵型のバタークッキーのようなものです。
11月2日の前に、子供たちが仮面をつけて歌を歌いながら家々を回り、儀式のためのケーキを乞い集めます。それが発展し、子供たちが家々を回りお菓子をもらうようになったのではないかと言われています。
トリックオアトリートの起源
1900年代初期のハロウィンで、いたずらっ子がお菓子をもらうためのおどし文句として使っていた言葉が子供たちの間で大流行し、そのまま定着したとされています。
また、1952年のディズニーアニメ「Trick or Treat」により、世界中に広まったという説もあります。
トリックオアトリートの単語をそれぞれ訳していくと、
いたずら (Trick)
それとも (or)
おもてなし(Treat)
といった具合になります。
しかし、この言葉はもともとこのような言い回しだったというのです。
私をおもてなししなさい。さもなくば、あなたをいたずらするぞ
そうだとすると、
トリート・オア・トリック
になるはずです。
しかし、順番を変えたほうが英語圏の人にとっては言いやすかったので、
トリック・オア・トリート
になったのだとか。
いずれにせよ、お菓子をくれない場合には、本当にいたずらをしても良いそうです。
お菓子をくれなかった家に仕掛けるいたずら
お菓子をくれなかった場合のいたずらの例がこちらです。
- 玄関に生卵を投げつける。
- 家の外壁に向かって水鉄砲で水を噴射する。
- 庭先の木の枝にトイレットペーパーを巻き付ける。
- パーティースプレーで家をデコレーション。
これらの例は一部ですが、アメリカでは行き過ぎたいたずらが少し問題になっているようです。
では、「トリックオアトリート」と言われたときに、どう返事をすれば良いのでしょうか?
トリックオアトリートへの返事
「トリックオアトリート」と言われたときの定番の返し言葉は2つあります。
ハッピーハロウィン
トリート
仮装した子供たちが「トリックオアトリート!」と言ったら、ぜひとも「ハッピーハロウィン!」や「トリート!」と返してあげてくださいね。
さて、ハロウィンでは仮装を楽しんでいますが、それはなぜでしょうか?
ハロウィンで仮装する理由


ハロウィンの時期には、死者の魂と共に、悪霊や魔女もこの世にやってくるとされています。そして魔女や悪霊は、生きている人間から魂を奪うという言い伝えがあります。
そこで、人々は自分たちが人間だと気付かれないように、悪霊や魔女になりすますために仮装するようになったと言われています。
意外と少ないハロウィンの研究本
大人向けのハロウィンの解説書があります。
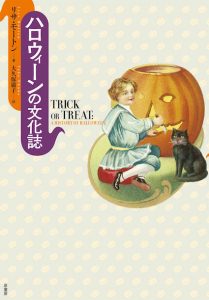
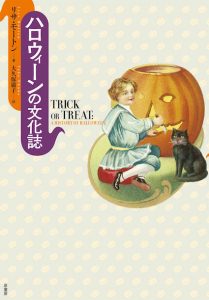
『ハロウィーンの文化誌』
リサ・モートン/著
大久保 庸子/翻訳
本体価格 2,800円+税
著者のリサ・モートンは、アメリカのハロウィン研究のリーダー的存在の方です。
不思議なお祭りハロウィンの起源・古代祭礼から始まり、ハロウィンが世界に広まっていくその過程と現在の姿を、たくさんの図解を用いて紹介されています。
ハロウィンにまつわることは、とにかくたくさんの説があります。一体どの言い伝えが本当に本当の事実なのか?その謎に迫る一冊です。
まとめ
ハロウィンは、様々な行事や儀式、習慣が入り混じってでき上がった、ちょっと変わったお祭りです。仮装やかぼちゃの飾りを楽しむ人が多いですが、元は宗教的行事のようです。
それぞれの意味や由来を知ると、ハロウィンがますます楽しくなりそうですね。
関連記事
ハロウィンは日本にいつから定着した?流行したきっかけと理由
【ハロウィンネイル】簡単なやり方やシンプルなデザインまとめ
ハロウィンのネイルアート!セルフで簡単なやり方まとめ
ハロウィンのネイルシール!100均のシンプルなデザインまとめ













