お月見どろぼうの意味と由来は?風習が残る地域と配るお菓子の種類
本サイトにはプロモーションが含まれています。

秋と言えばお月見ですね。
古来より日本では、お月さまを特別な存在として崇める風習があり、お月さまにちなんだ行事がありました。
「お月見どろぼう」という行事をご存じでしょうか?
古くから各地に伝わる行事で、十五夜の日だけ、子供たちはお供え物のお団子を盗んで良いとされる行事です。
そこで、お月見どろぼうの意味や由来、行われている地域やお供えのお菓子の種類などを紹介します。
お月見どろぼうの意味と由来
お月見どろぼうの起源と言われている風習
その昔、山間の農村部において、このような風習がありました。
月の光がひときわ明るい十五夜の晩にだけ、よその畑から里芋を盗んでも良い
というものです。
盗むときは、道から片足だけ畑に踏み入れたところまでとされていました。
それが片足御免という風習です。
他にも、似た様な風習があります。
襷(たすき)一ばい
十五夜の晩にかぎり、襷で結わえられる分だけは盗んでも良い。
まんだかな
お供えが済んだら、すぐ子供がお供え物を取って行く。
「片足御免」が、後に「お月見どろぼう」へと変わっていきます。
片足御免からお月見どろぼうへ
ときは戦前から昭和中期ごろのことです。
「片足御免」と同じく山間の農村部において、十五夜の晩だけは、子供たちがよその家に入り、お供えのお団子を盗んで良いという行事が広まりました。竿状の棒の先に釘や針金をつけ、そこにお団子をひっかけて盗むというものです。
これが、現在に伝わるお月見どろぼうです。「だんご盗み」「だんご刺し」「だんご突き」など、地域によって呼び名が異なります。
なぜお供えのお団子を盗んで良いのかというと、子供たちは月からの使者と考えられていたからです。
- お団子を盗られることは縁起が良い。
- お団子を盗られた農家は豊作になる。
- 盗んだお団子を食べた子は長者になる。
- 七軒盗んで食べると縁起が良い。
お団子をお供えする家庭も、縁側や庭先にお団子を置いて、子供たちが盗みやすいように工夫をしていたようです。
食糧不足の真っただ中において、このような行事が広まり始めたのは、信仰的な理由だけではなさそうですね。せめてお供えのお団子くらい、子供たちにお腹いっぱい食べてほしい。大人たちのそんな思いが込められていたのかもしれません。
現在のお月見どろぼうのあり方
現在のお月見どろぼうは、名称はそのままですが、お供えの品や子供たちの盗み方に変化が見られます。
子供たちが
「お月見くださ~い」
「お月見どろぼうで~す」
と声をかけて各家庭を訪れ、お供えのお菓子をいただいていきます。
掛け声は地域によって異なっていて、三重県南部の東紀州近辺では「たばらして~」と言います。これは、お供え物を「賜る(たまわる)」が転じて「たばらう」となったと言われています。
一部の地域では、竿先にお団子をひっかける風習が残っているようです。
では、お供えの品はどの様なものでしょうか?
お月見どろぼうで配るお菓子の種類とやり方
配るお菓子の種類
お月見どろぼうの季節になると、地元のスーパーマーケットでも、お月見どろぼう用のお菓子セットなどが売り出されます。食料品店のお菓子売り場で、普段から販売されているようなお菓子を用意するのが一般的です。
盗みにくる子供たち全員に行き渡るようにするのが理想的で、お菓子が高価である必要はありません。むしろ駄菓子のようなお菓子で、数をたくさん用意することが望ましいです。
家庭によっては、子供と一緒に手作りのお菓子を作るなど、そういった楽しみ方もあります。
お供えをする家庭の準備


- 子供たちが持って行きやすいように、個包装のものが中心です。スーパーや駄菓子屋さんで売っているようなお菓子を用意します。
- 手作りのお菓子を作る場合は、1つずつ取れるように切り分けるなどして、子供たちが持って行きやすいように工夫します。
- 用意するお菓子の数は、町内や区域の子供が1人1つ、多くても2つずつ持って行けるだけの量を用意します。少し多めに用意しておいて、訪れた子供全員がもらえるように配慮するといいです。
- 置く場所は「玄関先」「庭先」「縁側」など、靴を履いたままでもさっともらっていける場所がいいでしょう。台やテーブルを用意してそこにお供えします。
お供えをもらう子供たちのルール
お供えをもらう子供たちの基本的なルールです。
- お菓子を入れるビニール袋を用意します。各家庭からお菓子を1つずついただきますが、意外とたくさんになります。大きめの袋が望ましいです。
- お家の敷地に入るときに、大きな声で「お月見くださ~い」「お月見どろぼうで~す」など、決められた挨拶をします。
- いただくのは1人1つまでです。お家の方が「1人2つまでね」と言ってくれたり、張り紙に「1人2つどうぞ」などと書いてあったりする場合は、2つもらっても構いません。
- お家の方がいたら、お礼を言って帰ります。
- 地域の子供たちのための行事ですので、住んでいる地域外に次々と出向いて、お供え荒らしをして歩くような行動は慎みます。
細かいルールは地域によって異なります。
外に設置されたテーブルの上からお供えをいただく場合もあれば、インターホンを押して、玄関先でその家の方から直接お菓子をいただく場合もあります。
お月見どろぼうを行っている地域一覧
2016年時点のGoogle Mapによると、こちらの地域でお月見どろぼうが行われています。
福島県塙町(台宿を中心に多くの地区)
福島県いわき市田人(廃れていた行事を復活させたもの)
福島県棚倉町近津(近津~八槻の街道沿い)
福島県棚倉町逆川
福島県棚倉町高野
福島県浅川町…町内
茨城県日立市日高町
茨城県久慈郡大子町?
茨城県稲敷市
茨城県稲敷郡美浦村
茨城県稲敷郡阿見町
茨城県笠間市岩間地区(旧岩間町。2014年まで確認。最近では見られないとのこと)
千葉県袖ヶ浦市横田
千葉県君津市
千葉県君津市久留里
千葉県君津市清和
千葉県富津市桜井
東京都多摩市?
山梨県甲府市?
三重県四日市市(多くの地区に残る)
三重県桑名市(一部の地域)
奈良県生駒市上町
大阪府岸和田市?
大分県大分市大在
鹿児島県与論島
沖縄県宮古島(シーシャガウガウという行事で、子供たちが獅子舞いをして各家庭を回りお駄賃をもらう)
お月見どろぼうやその他の風習・文化がわかるおすすめの1冊
日本の四季の行事やお月見どろぼうについて、こちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。
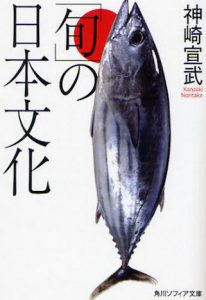
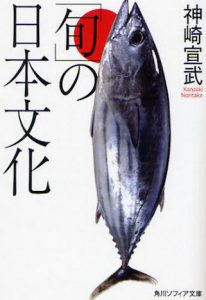
『「旬」の日本文化(角川ソフィア文庫)』
神崎 宣武 角川学芸出版
定価 679円(税込み)
著者である神崎宣武さんは、岡山県出身の民俗学者であり、旅の文化研究所の所長でもあります。
『「旬」の日本文化』では、日本に古くから伝わる四季折々の行事の意味や、歴史文化的な背景などが丁寧に記されています。我々日本人が、かつて自然や神々とどのように付き合ってきたのか、各地に伝わる行事や風習、言い伝えなどからその歴史を読み解く内容です。
お月見どろぼうについても載っています。お月見どろぼうをきっかけに、もっと日本の行事を知りたくなった方は、ぜひご一読を。
まとめ
お月見どろぼうには、収穫の喜びを分け隔てなくみんなで分かち合おうとする思いや、子供たちに対する思いやりが込められていたようです。子供たちは地域の行事の中で、社会のしきたりや礼儀を覚え、節度をわきまえることを学んでいったのでしょう。
お月見どろぼうが現在でも受け継がれている背景には、人と人とをつなぐ助け合いの精神と、子供たちの健やかな成長を願う大人たちの、昔と変わらぬ思いが込められています。
このような風習は、これからも受け継がれていってほしいですね。
関連記事
2016年のお月見の日程はいつ?満月を見られる日にちも調査
中秋の名月の意味・由来や読み方は?十五夜との違いも説明













