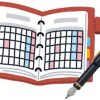年賀状はいつまで出せる?返事が遅れた場合や寒中見舞いとの違い
本サイトにはプロモーションが含まれています。

正月三が日を過ぎると、いつまで年賀状を出せるのか気になり始めますよね。
出すのが遅くなった時は寒中見舞いとして出すと言われていますが、年賀状との違いも気になるところです。
そこで今回は、年賀状を出せる期間や返事が遅れた場合の対応、寒中見舞いとの違いについてまとめてみました。
年賀状はいつまで出せる?


年賀状は、1月7日までに相手に届けば良いとされています。
1月1日〜1月7日は松の内(まつのうち)と呼ばれていて、正月の松飾り(門松)を飾る期間のことを言います。
(関東では1月7日まで、関西では1月15日までを松の内とするところが多いです)
年賀状は新年のお祝いの挨拶状なので、松の内に送るのが良いというわけですね。
ただ、都合で返事を出すのが遅れたり、出していない相手から遅れて届いたりして、投函するタイミングが遅くなってしまう時がありますよね。
そのような時はどうすれば良いのでしょうか?
年賀状の返事が遅れた場合


年賀状が1月7日までに相手に届かない場合は、寒中見舞いとして返事を出します。
寒中見舞いとは、寒い季節に送る季節の挨拶状のことです。年賀状を出すのが遅くなったり、喪中で年賀状を出せなかったりした場合の代用として使います。
年賀状の代わりとして寒中見舞いを出す場合は、返事が遅れたことに対するお詫びの一言を添えると良いですね。
寒中見舞いの文例1
ご丁寧な年賀状を頂きありがとうございました
新春のご祝詞を頂きながらご挨拶が遅れましたこと深くお詫び申し上げます
厳しい寒さの折 風邪などお召しになりませんようご自愛ください
今年もよろしくお願い申し上げます
寒中見舞いの文例2
厳しい寒さが続いておりますがいかがお過ごしでしょうか
お風邪など召しませぬようご自愛ください
またお会いできる日を楽しみにしております
喪中の相手に送る場合の文例
ご服喪中と存じ年頭のご挨拶は遠慮させていただきましたが
皆様いかがお過ごしでしょうか
寒い日が続きますがお風邪など引かぬようご自愛ください
喪中の相手に年賀状を出してしまった時の文例
ご服喪中をわきまえず年始状を差し上げてしまい誠に失礼いたしました
寒さ厳しい折どうぞご自愛ください
喪中で年賀状が届いた場合の文例
ご丁寧なお年始状を頂きありがとうございました
喪中につき年頭のご挨拶を控えさせていただきました
今後も変わらぬお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします
では、寒中見舞いはいつからいつまで出せるのでしょうか?
寒中見舞いはいつからいつまで?


寒中見舞いは、1月8日~2月3日ごろまでに相手に届けば良いとされています。
1月8日は松の内(1月1日〜7日)の翌日、2月3日は立春(2月4日ごろ)の前日です。
「寒中」とは「小寒(しょうかん)」の始まりから「大寒(だいかん)」の終わりまでのことを言うので、「大寒」の終わりである2月3日ごろまでが寒中見舞いを出す期間となります。
ちなみに、2月3日を過ぎて相手に届く挨拶状は「余寒見舞い」と言います。いつまでという決まりはないようですが、一般的には2月末までとされています。
では、年賀状と寒中見舞いの違いは何でしょうか?
年賀状と寒中見舞いの違い
意味の違い
年賀状
新年のお祝いの挨拶
寒中見舞い
季節の挨拶
年賀状はお祝いの挨拶なので、喪中の時は出すことができません。
寒中見舞いは季節の挨拶でありお祝いではないので、喪中の時でも出せます。また、年賀状の代用としても使えます。
はがきの違い
年賀状
年賀はがき
寒中見舞い
官製はがき
寒中見舞いは官製はがきで出すのがマナーとされています。年賀状の代わりとして寒中見舞いを出すのに、年賀はがきで出したら意味がごちゃごちゃしますよね。
年賀はがきが余ったからといって、年賀はがきで寒中見舞いを出すのはふさわしくないでしょう。
郵便局で手数料(1枚5円ほど)を払えば、年賀はがきを官製はがきに変えてもらうことができます。高いわけではないと思いますので、寒中見舞いを出す時は官製はがきで出しましょう。
期間の違い
年賀状
1月1日〜1月7日
寒中見舞い
1月8日〜2月3日ごろまで
年賀状は松の内まで、寒中見舞いは立春(2月4日ごろ)の前日までに出します。
まとめ
年賀状は新年の挨拶、寒中見舞いは厳寒期に出す互いの近況報告を兼ねた季節の挨拶になります。
意味の違いはありますが、お付き合いのある方やお世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える挨拶状という点では同じですよね。
それぞれの意味を踏まえた上で、お返事を書いてみて下さいね。